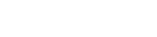『選挙研究』第41巻1号
はじめに 日本選挙学会2025年度年報編集委員長 境家史郎
『選挙研究』第41巻第1号をお届けします。
今号では「憲法と政治」を特集のテーマとし,依頼論文6本と査読付き論文1本を収録しました。近年,日本政治研究者の間で「憲法ブーム」というべき現象が起きつつあることをふまえた特集になります。
このブームをもたらした学術的背景(政治学における制度論の興隆,データセットの整備など)については,巻頭論文である待鳥聡史「憲法政治学の可能性」の中で詳しく議論されています。他方,日本に限れば,2000年代,特に第二次安倍晋三政権の登場によって,憲法改正問題が現実政治の争点としてクローズアップされるようになった――あるいは,日本政治の「再イデオロギー化」が進んだ――ことも,研究者の目を憲法に向かわせる,大きな要因になったと考えられます。
「憲法をめぐる政治学」の具体的論点やアプローチは多岐にわたります。このうち,本特集では「有権者の憲法観」――待鳥論文が挙げる「現在最も先端的だと思われる研究テーマ」のひとつ――に関する研究として,Kenneth Mori McElwainによる“Democracy by Design? Voter Preferences for Institutional Coherence in Japan”を収録しています。マッケルウェインは,サーベイ実験の手法を用いて,執政制度,選挙制度,地方制度について,有権者がどのような組み合わせを好んでいるのかを分析しています。結果の詳細は同論文に譲りますが,ここで得られた知見は,日本の現実の文脈における「憲法改革」論議(憲法典や憲法附属法の改革をめぐる論議)を考える上で大きな含意を持ちます。
続いて,芦谷圭祐・石間英雄「憲法と議論――国会議員は憲法とどう向き合ってきたのか」(査読付き論文)は,エリートレベルにおける憲法論議について,実証的に迫ろうとした研究です。同論文では国会会議録を量的テキスト分析にかけ,各政党が好んで取り上げる論点の種類やその時系列的変化を明らかにしています。著者らが主張する通り,「憲法典の特徴や世論の研究と比べ,政治的エリートの分析は十分ではなかった」という学界の状況があり,この研究はその間隙を埋めようとするものです。分析の結果としても,「国会において,『再イデオロギー化』しているのは,共産党と社民党だけ」といった,日本政治論にとって含意に富む知見が示されています。
量的分析アプローチを採るこれらの研究とは対照的に,竹中治堅「日本の安全保障政策の展開と憲法解釈――憲法規定の曖昧さと内閣の裁量」では,戦後日本の憲法政治の重要側面について,歴史的に丹念に跡付ける作業が行われています。すなわち竹中は,占領期以来,今日までの日本の安全保障政策を精査し,それが日本国憲法の枠を逸脱するとはいえないこと,言い換えれば,戦後日本の政体は「十分に立憲的であった」ことを主張しています。その際,竹中は,憲法9条の文言――広い解釈の余地を残す――だけでなく,国会多数派の意思が常に反映されてきたことを重視していますが,これは政治学者ならではの憲法論といえるでしょう。
以上の4論文(待鳥,McElwain,芦谷・石間,竹中各論文)は「憲法に関する政治学的(政治学者による)研究」ですが,逆に,「政治(制度)に関する憲法学的(憲法学者による)研究」もまた,近年,特に比較的若い世代の研究者の間で活発化しています。その点をふまえ,編集委員会は今回,3人の憲法学者に「憲法と政治」に関する寄稿を依頼しました。
まずSatoshi Yokodaidoによる“Article 9 of the Japanese Constitution and Constitutional Scholarship in Japan”では,憲法問題の天王山たる「9条問題」について,日本の憲法学者がどのように反応してきたかを論じています。2014年における政府の9条解釈変更(集団的自衛権行使の一部容認)に際して,その決定に反対するという政治的目的のために,従来の憲法解釈をなし崩し的に修正する(従来,違憲と見てきた自衛隊の存在を事実上許容する)憲法学者の動きがあったことを指摘しています。筆者(境家)のような政治学者の目から見ると,当論文は,それ自体政治的アクターである「憲法学者」集団のメンタリティを理解する上で貴重な情報を含みます。また,こうした指摘がほかならぬ憲法学者から示されたことは,「憲法学者」が実際のところけっして一枚岩的な集団ではない,という(当然の,しかしステレオタイプに反した)事実にも改めて気づかされます。
Yokodaido論文でもふれられていますが,日本の戦後憲法学には「抵抗の憲法学」と「制度の憲法学」という2側面――「活動家」と「法学者」の2面と言い換えてもよいでしょう――があるとされます。このうち,かつては前者が圧倒的であったところ,世代交代に従って,前者と後者のバランスがとれた状態へと移行しつつある,というのが戦後憲法学の大きな流れであるようです(高橋和之の議論参照)。
本特集では,「制度の憲法学」研究の実例として,2本の論文を取り上げました。いずれも政党(組織およびその活動)をめぐる制度設計を考える上で,重要な視点を含んでいます。まず村西良太「政党の自由と国庫助成――ドイツ連邦憲法裁判所判決の展開に示唆を求めて」は,ドイツにおける政党国家助成制度の内容およびその形成過程について,連邦憲法裁判所と連邦議会の攻防に焦点を合わせつつ論じています。石原佳代子「政党内部における指導者選出に関する考慮要素――ドイツの事例をもとに」は,やはりドイツのケースについて,政党内指導者選出に関する法的(基本法や政党法による)要請や,各党における実際の運用について詳細に検討されています。両論文はいずれも,政党のコンプライアンスが問題視されている日本の現状をふまえ,実践的にもきわめて有益な示唆を含んでいるといえるでしょう。
以上7本の論文で「憲法と政治」をめぐる論点がすべてカバーされた,とはまったく考えられません。例えば,待鳥論文が指摘するところ,憲法(典)の国際比較が「現在最も先端的だと思われる研究テーマ」のひとつとしてあるわけですが,本特集では残念ながら,この点に直接関係する研究を収録することはできませんでした。『選挙研究』のみならず,日本でも政治学関連の各学術誌において,継続的にこのテーマを探求していくことが求められます。今回の特集はその一歩として見るべきものでしょう。
最後に,『選挙研究』への投稿および採択状況をお知らせいたします。2024年10月から25年3月までの間に3本の投稿があり,それ以前に投稿されたものも合わせて,25年3月末時点で3本に掲載可,2本に掲載不可の判定が下されております(その他,査読プロセスの途上にあるものが1本)。査読通過論文3本のうち1本は特集論文として,他の2本は「研究論文」として今号に収録されました。引き続き,会員からの積極的な投稿をお待ちしております。